「創作した漢詩を生成AIにて具現化する試み」で、「学習パートナー」としての生成AIの可能性を探る ~筑波大学附属駒場中・高等学校

筑波大学附属駒場中・高等学校では毎年、高校2年生の漢文の授業で生徒全員が漢詩の創作に取り組んでいます。今年はさらに美術の授業で、画像生成AI「Adobe Firefly」を用いて、生徒たちが自作の漢詩を1枚の絵として表現する活動にチャレンジしました。漢詩の創作活動と画像生成AIによるイメージの具現化を組み合わせることで、学びにどんな広がりや深まりがもたらされたのか、同校の芸術科・美術主幹教諭 川人武先生と国語科教諭 有木大輔先生にお話をうかがいました。
漢文と美術の教科横断の取り組みのきっかけ

筑波大学附属駒場中・高等学校の芸術科・川人武先生(写真左)と国語科・有木大輔先生(写真右)
漢文と美術という教科を横断した新たな取り組みのきっかけは、川人先生と有木先生の雑談だったといいます。ある時、有木先生が10年以上試行錯誤しながら授業で生徒たちと取り組んでいる漢詩創作の話題に。日頃から生徒たちの作品(表現)を評価する必要があった美術担当の川人先生は、「生徒が作る漢詩の良さをどのように判断するのか?」という問いに対する有木先生の「良い漢詩は1枚の絵になる」という言葉に、非常に興味をひかれました。漢詩は、時系列のあるストーリーよりも、1つの心象風景や情景を切り取るような一場面で完結する世界観に収まる作品が好ましいとのこと。それを聞いた川人先生は、「良い漢詩をそのままプロンプト(指示文)にしたら、1枚の絵ができるのでは」と考えたのです。そのアイデアに盛り上がったお二人は、実際に授業で実践してみることになりました。
画像生成AIを表現の道具として使ってみる授業
有木先生が担当する漢文の授業では、高2の1学期に生徒全員が漢詩を創作しています。漢文の授業は週に1コマ、1学期間の実質5~6時間ほどで、押韻や平仄などの漢詩の基礎を学んだうえで漢詩を一首作って提出する、という課題に取り組みます。その中で美術を選択している生徒43名が、自作の漢詩をもとにAdobe Fireflyで画像生成に挑戦しました。
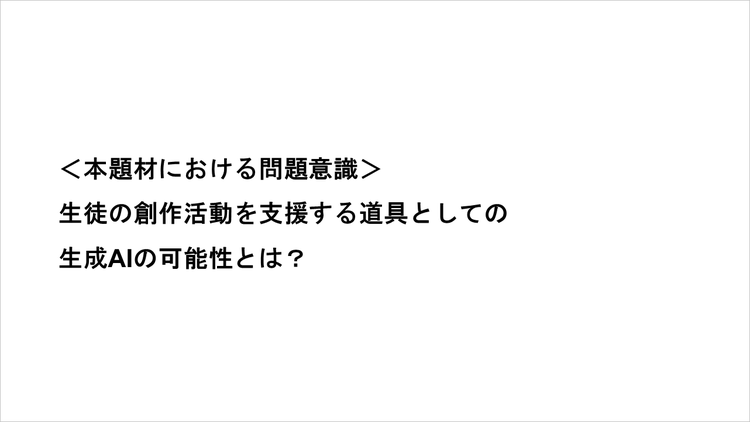
今回の実践については、「“ものづくり”に画像生成AIがどのように活用できるのだろうか、ということが知りたくて取り組んだ」と川人先生は語ります。「漢詩作りも、美術の造形表現も、どちらも創造的な表現活動です。そして、その2つを組み合わせて表現することは古くからあり、決して珍しくはないのですが」としたうえで、川人先生は「そこに画像生成AIを使うとはたして何が起こるのか、やってみないと見えないことが多々あるだろう、と。だから1回やってみて、生徒がどのような反応を示すのか、どんなものが生み出されるのかを見ていくことで、『創造的な活動において、我々は画像生成AIという道具にどう向き合っていけばよいのか』を考えてみたいと思ったんです」と続けます。
形にすることそのものが目的ではなく、形を作っていく行為の過程で人の認識にどのような変化が起きうるのかを注意深くとらえていくことで、「モノを作ることの意味」を考える手がかりがつかめるのではないか、と考えつつ、生徒の様子を見ていくことにしました。
授業にはAdobe Fireflyを活用
授業ではアドビの画像生成AI「Adobe Firefly」を活用しました。Fireflyを選んだ一番の理由は、「著作権的に安心である」ということ。「Fireflyは権利関係のリスクがクリアになっているツールであり、直感的でわかりやすいインターフェースであるということも含め、授業で使うにはこれだと思いました」。
ほかにも、「ブラウザから簡単に使える」「アドビ製品(Photoshopなど)との連携ができるのでスムーズな活用が可能」という点もFireflyのメリットだと川人先生。以前より、筑波大学附属駒場中・高等学校では全校生徒が「Adobe Creative Cloud」のライセンスを保有し、PC教室やBYODで使用しています。授業での活用はもちろん、生徒たちは「課題研究」や学術オリンピックをはじめとする各種コンペの発表資料作成などに積極的にCreative Cloudを使いこなしています。「高校1年の美術では、Photoshopに搭載されたFireflyの生成塗りつぶし機能を使った授業をしています。その経験もあって、生徒たちはFireflyを戸惑いなく使うことができました」。
当初、国語科の有木先生は「作文などの場面では、生成AIは弊害のほうが多いという先入観があった」ことから、教育現場での生成AIの活用には懐疑的でしたが、「川人先生の話を聞いて、やり方次第で生成AIは無限の可能性が広がっていくなと認識が改まりました」。
漢詩をそのままプロンプトにするのではなく様々な工夫を試みる
実際の授業はまず、漢詩の名作、孟浩然の「春暁」を使って、実験的に画像を生成してみせることから始めました。
1) 漢詩をそのままプロンプトとして入力し、画像を生成する
2) 書き下し文や日本語訳をプロンプトにしてみる/画像のスタイルを変えてみる
3) 日本語訳を、さらに英語に翻訳してプロンプトにする
と段階を踏んで、画像生成を試みて、漢詩そのものをプロンプトにして画像生成するのは難しいことを生徒と一緒に検証しました。

漢詩をそのままプロンプトにして画像を生成

日本語訳をプロンプトにし、画像スタイルをアートにした画像生成

英語に翻訳してプロンプトを入力し、画像を生成
その結果を踏まえたうえで、次はいよいよ生徒たちが自作の漢詩で画像生成に挑戦です。最初は自分の漢詩をそのままプロンプトとして入力するところからスタート。続いて、「自分が漢詩を作った際に頭の中で描いていたビジョン」に画像を近づけていくため、必要に応じてプロンプトを工夫してみようと川人先生は生徒に投げかけたそうです。「プロンプトとして詩をまったく使わなくてもいいし、詩以外のコメントや指示を追加してもいい。なんなら、自分の詩そのものを変えてしまってもいいよ、と。自分で工夫してプロンプトを組み立てて“自分が詩で表現したかったイメージ”を画像にしてごらん、と促したんです」。
与えられた2コマの授業時間の中で、生徒は様々な方法を自由に試しながら画像生成に取り組みました。最終的に最も自分のイメージに合う生成画像を1点選び、Illustratorで漢詩と組み合わせてレイアウトしたうえで、作品として提出しました。
生徒の姿から見えてきた生成AIの2つの使い方
創作した漢詩から生成AIで画像を生成する活動を通して、
①生成画像を、自分が思い描いていたイメージに近づけようと工夫を重ねる生徒
②生成画像が自分のイメージとは異なっていても、思いもかけない画像が生成されることに面白みを感じる生徒
という二通りの反応をする生徒の姿が確認できたと川人先生、有木先生は分析します。
<①生成画像を、自分が思い描いたイメージに近づけようと工夫を重ねる生徒の作品例>
自分の詩の世界と生成結果に距離があると感じた生徒は、自分なりにプロンプトに工夫を重ねて、自分がイメージする情景に近づけようとしました。

余分な形容詞などを省いた単語の羅列をプロンプトとして入力してみたという生徒の作品

現代語訳して、さらに描写を追加したプロンプトを入力。生成された画像をさらにPhotoshopで加工して作りこんだ作品
「生徒の漢詩だけを読んだ時と、イメージとして出してきた絵を見た時で、詩の印象が違うという発見がありました」(有木先生)
<②生成結果が自分のイメージと異なっていても、思いもかけない画像が生成されることに面白みを感じる生徒の作品例>
漢詩をそのままプロンプトで入れた生成結果の段階でも、「面白い」と肯定的に受け止める生徒もいたそうです。

書き下し文を入れただけで面白いと感じる絵が生成できたという生徒作品。スタイルを変更してみたらさらに深みが増したという
「最初に生成した絵も良かったが、それだけでは飽き足らず、スタイルを『彫紙』にしてみたらそちらのほうが良いと思ったという例。生徒の中でこの絵に行きつくまでに、詩の新たな解釈が画像としてどんどん示されるところが、国語を超えた面白い部分だと思います」(川人先生)
「制作(表現)のパートナー」「鑑賞のパートナー」という生成AIの2つの役割
①と②の2パターンの生徒の反応から、画像生成AIには次のような学習の広がりを促す可能性があるのではないかと川人先生、有木先生は考えています。
①(=表現者としての視点)
プロンプトを工夫していく過程で、自分がどのようなことを表現したかったのかが整理されていくことで「制作意図(テーマ)」の明確化が見込め、作品の推敲にもつながる
②(=鑑賞者としての視点)
想定していた情景と異なる画像に対し、他者が自分とは別の見方で作品を受け取る可能性があると肯定的に受け止めることで、作品に対する新たな解釈との出会いや視点(ビジョン)の獲得が見込める
①は創作活動への寄与、②は作品の鑑賞・理解への寄与と言い換えても良いでしょう。
授業終了後の生徒へのアンケートでは、「画像を自分のイメージに近づけるために、自分の漢詩を修正したいと思いましたか?」という質問に対し、3割強の生徒が「修正したいと思った」と回答しました。「我々は最初、どちらかというと生成AIとのやり取りは『鑑賞者同士の対話』のようになるのかなと思っていたんです。ところが『作り手としてのパートナー』という意識で接していた生徒もかなりいて」と驚きを語る川人先生。有木先生は「今までは生徒が漢詩を提出したところで課題は完了でした。3割もの生徒が『自分の作品をもう一度作り直してみたい』という意識に持って行けたところにすごく価値があります。国語としてはそれがまさに推敲ということで、それだけでもう狙い通り、成功だと思っています」と振り返ります。
「学習パートナー」としての生成AIの可能性と価値
画像生成AIには「制作(表現)のパートナー」「鑑賞のパートナー」という二通りの可能性があると確認できたところが、今回の実践の最も大きな成果だと感じているお二人。生成AIを学習のパートナーとして活用することの価値をいくつか挙げていただきました。
まず1つ目は、生成AIをパートナーとすることで生徒たちの心理的安全性が高まる可能性があること。生徒たちの中には、自分の作ったものをなかなか外に出したがらない子もいます。そういった子たちにとっては、クラスメイトとペアになって行う活動よりも取り組みやすくなるであろうと想像できます。
2つ目は、人間とはスピード感がまったく違うこと。今回の実践でも、漢詩をもとに誰かに絵を描いてもらうというやり方も考えられますが、それだとかなりのタイムラグが生じますし、何度もやり直してみることは難しくなります。
ただ、上記2つのポイントはAIの確実なメリットである一方で、人間同士で行う活動にも別の価値があることも事実です。生成AIは何かに取って代わるものではなく、新しい切り口が1つ現れたというのが、お二人の現状の認識です。
これからも何らかの形でこうした実践を続け、画像生成AI活用の結果や経験を蓄積していけたらと語る川人先生。また有木先生は、他校で同様の実践をする場合、漢詩の創作はハードルが高ければ、既存の漢詩や和歌、俳句を用いた授業でも画像生成AIを活用した学びが展開できるのではないかとアドバイスを送ります。
今回の筑波大学附属駒場高等学校での取り組みは、今後の教育現場における生成AI活用の新たな価値や可能性を広げる大きなヒントとなりそうです。